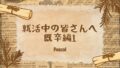今年も全国の高校の大学合格実績が各雑誌で発表されていますが、今回は桐蔭中等教育学校の進学実績について書かせて下さい。
まず、ややこしくて色々な人が誤解している桐蔭学園の現状ですが、昔あった別学で高校からの外進生と高校で混ざる中高一貫校(今でいう桐光学園に似た形)としての桐蔭学園中学は廃校になっており、一時は少数精鋭をうたって既存中学とは一線を画した男子校として誕生した中等教育が、共学として再スタートを切ったのが今年卒業する共学1期生からでした。男子校としての最後の期だった1年前の進学実績が前年に比べて物足りなかったことから、今年の中等教育の中学入試は人気が前年に比べて低かった印象です。
昔のように進学実績を上げるために、ほぼ全科目で能力別クラスを実施し、修学旅行も行かない、高校から入ってくる外進生と切磋琢磨し、というような方針ではなく、生徒の自主性を重視し、アクティブラーニングのような形の授業を増やすなど非管理型で再出発した中等教育について、進学実績は低空飛行になると予想していた人も多かったのではないでしょうか?
それが蓋を開けたら、理Ⅲを含む東大が5人という数字には正直驚きました。一部の他校のような科目の多い国立受験を諦めて難関私立で合格実績をかせぐという方針ではなく、あくまで国公立を基本に据えたことが東大5人や北大4人という数字に表れているのかもしれません。この5人という数字は、人数が倍いて偏差値が近い桐光学園の3人や偏差値が上の世田谷学園の2人や早慶にめっぽう強い頌栄女子学院の4人を上回っています。
早慶でいうと、早稲田の14人という数字は物足りないですが、慶應の18人はそれなりに多く、あとは青学の39人という数字が目立っている印象です。
今回の東大5人という数字が来年どうなるのか、昔の管理型を捨て、アクティブラーニングのような方針で進学実績でも成功している広尾学園や三田国際のような道を進むのか、どんな学校になっていくのか来年以降も注目していきたいと思います。