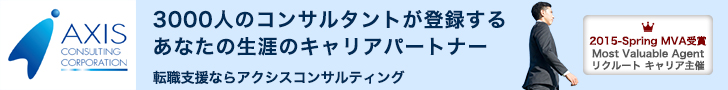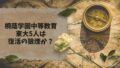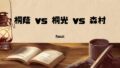今回は最近ニュースになることが多い、日産自動車について書かせてもらおうと思っています。
日産の歴史
まずは、日産のこの数十年の歴史から振り返ると、2000年前後に経営危機に陥ったことをきっかけにカルロス・ゴーンがルノーから派遣され、工場閉鎖等の固定費削減や車種削減に取り組む日産リバイバルプランを実行しました。一方で電気自動車にいち早く目を付け、リーフという形で世に送り出しました。今振り返ると、この時の車種削減とリーフの戦略が、今の日産の苦境の一因になっていると感じます。
日産の業績低迷の理由は筆者は大きく2点あると考えていまして、一つ目は日産の経営と組織の体制、二つ目は上でふれた電気自動車含む車種戦略です。
外国人マネジメント+官僚主義
一つ目の経営と組織の体制というのは、外国人がマネジメントの多くを占めることによる弊害と、旧来の日本人中心の官僚主義体制による弊害が、悪い形で合体してしまっている点を指しています。日産という会社はルノーの資本が入っていた時代は、外資系で外国人マネジメントは多いが、日本に本社があり従業員に日本人が多いという、いわゆる日本に多くある外資系企業(本社は外国)とは少し違う特色を持っていました。この日本にいる日本人従業員にとって、いくらグローバル戦略として米国や中国のマーケットを重視し、日本向けの車種を限定することが効率のいいと言われても納得感が十分ではなく、経営と現場の間に溝が広がっていったと考えます。この溝は新車開発から営業に至るまであらゆる領域でのパフォーマンス低下の要因になっていたのではないでしょうか。
官僚主義というのは、外国人マネジメントとは別の話で、日産が旧来から持っている性質による弊害を指しています。日本の旧来の役所をイメージしてもらうと分かりやすいと思いますが、階層が多く意思決定に時間がかかる、社歴や学歴のようなヒエラルキーが幅をきかせている、他社を含む外部のより良いやり方を取り入れない排他主義、特にこの排他主義は、新卒で入った社員が昔から受け継がれている時代遅れな伝統も含めて固執し、外部から転職してきた優秀な人材の持っているやり方に変えるなんていうことはほとんどない(そもそも聞かれもしない)という話をよく聞きます。転職市場では採用が活発だった日産ですが、転職してきた人間のナレッジを活かせないとなると、単なる人員補充をしていただけで、業績がそこから良くなっていくというのは全くないことになります。
外国人マネジメントから降ってきた納得感のない戦略と従来からの官僚主義という二つの負の要素によって、現在の日産の競争力の低下の一つの要因になっていると考えます。
車種戦略について
二つ目の電気自動車を含む車種戦略についてですが、電気自動車を重視したため、ハイブリッドを軽視することにつながり、ハイブリッド車の需要の高い日本でさえ競合他社に比べてラインナップが少なく、e-powerという仕様を増やしたものの、今度は航続距離の長い米国でハイブリッド人気が出て、少し前に日本マーケットでハイブリッド車不足で苦労したことと同じことを米国マーケットでやってしまっている状況です。さらに、上でも述べたリバイバルプラン時代の車種削減により、日本マーケットを例にとっても、スバルやマツダのように独自路線で人気を得ることも難しくなり、メジャーな車種では、ノートこそ販売台数で競合他社と競っている部分ありますが、セレナがノア+ヴォクシー+エスクエイアに負け、エルグランドはアルファード+ヴェルファイアに大敗、軽自動車ではダイハツやスズキに及ばずに、マーケットシェアは2位争いどころか5位争いのような状況です。
今後の展望は・・
これらの状況を踏まえると、外国人マネジメントが変わる気配もないですし、官僚組織もすぐに変われるものでもないので、ホンダの子会社として再出発する選択肢も蹴ってしまった現状をとらえると、このままズルズルと業績が下がってくるのではないかと考えています。4月から始まる予定のトランプ政権による追加関税25%もメキシコ工場の分にヒットすると思うので、明るいニュースがなかなか出てこない状況だと思います。