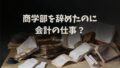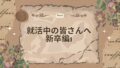今回は受験について、計画的に受験とキャリアを考えようという話とは少し違う角度で話をさせて下さい。賛否両論あることは承知の上で書かせてもらいますが、人生のピークが中高大になることのリスクが少し怖いと考えています。偏差値の高い学校に合格したはいいものの、何とか在学中はしのいだとしても、優秀な同級生の華々しいその後の人生と自分を比較し、完全に負けたと感じた場合、音信不通になるというケースを数多く見てきました。自分もそういう形で距離を取ることになったグループというのはそれなりの数あります。例えば、かなりの割合の同級生が弁護士になっている慶應法学部のゼミの同窓会や、多くの経営者や会社役員になっているITベンチャーの同僚とのつながりがそうです。レベルの高い人に囲まれて切磋琢磨することは素晴らしいことですが、人生はどちらかと言えば尻上がりに登り詰めたほうが幸せだと思っており、30年後の到達点が同じでも、下って到達するよりも、登って到達するほうがいいと考えています。
この話が自分の子供の中学受験につながるのですが、うちが塾にほぼ頼らずに受験をしていたのは、塾のシステムである1対多という仕組みが子供に合ってなかったというのもありますが、それ以上に塾がかかげる華々しい合格実績の裏で偏差値重視で4連敗して第5志望に行くことになった自分のようなケースがあることや、当然偏差値の高い学校を目指すべきだという風潮に子供をさらしたくなかったという理由が強いです。自分が進学した第5志望の学校も、今考えればいい学校でしたし、今でも多くの同級生とは連絡を取っていますが、当時の自分は何で第5志望の学校に行かなければならないのか?というネガティブな思考に支配されていました。
中学受験の奮闘記はまた別で書かせてもらいますが、親として子供にもっとプレッシャーをかけて勉強をさせることはできたかもしれないのですが、やはり10年以上の長いスパンで見たときに、中学受験の第1志望に行くのか第3志望に行くのか、そこまで大きな差にはならない、逆に仮に出口の大学が同じだった場合、偏差値の高い学校から当然のように進学するよりも、少し偏差値の低い学校から進学したほうが、同じ大学でも本人の感覚や周りからの反応がよりポジティブなものになるのではないか?と思ってしまい、そこまで追い込むことはできませんでしたし、進学先も特に下の子は管理型で勉強をいっぱいやらせる学校ではなく、ある程度自由にやらせてくれる学校にしました。もちろん、向上心が強く負けず嫌いな子であれば、ちょっと背伸びしてでも優秀な同級生がいる学校に行くということは賛成ですが、それでも6年後の大学受験や10年後の就職やさらにその先を考えると、あまりに早い段階でエリート層の仲間入りをすることが幸せかどうか、超難関校の受験風景等を見ているとついつい考えてしまいます。